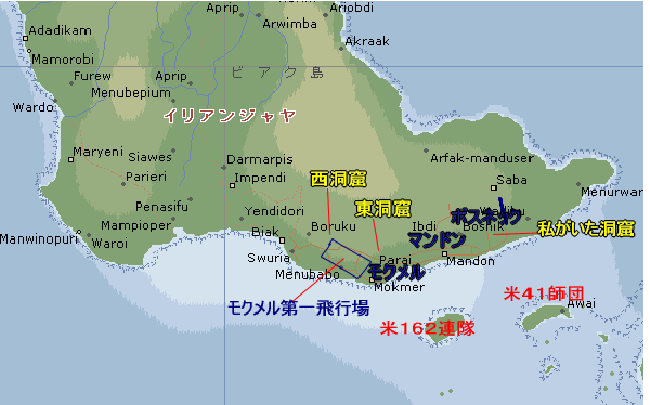 |
| 私がいた洞窟の位置は、ボスネックの入り江が直ぐ見えるところでした。 |
同年5月24日、警戒中の哨戒機から、「空母二隻を含む、連合艦隊がビアク島方向に進行中、数日中に到着の予定」との報を受けていた。いよいよ決戦の日が近いと感じた我々は、全員それぞれの陣地で戦闘準備についた。
私は、鎌田分隊長の指揮で、ボスネック港近くの鍾乳洞に入っていた。
この洞窟の入口は、縦横約2メートルあり、横穴を降りるように進むと瓢箪のように広く、奥行きは30メートル位で、5〜60人は十分入れ、南国の暑さを凌ぐには格好の場所でもあった。
尚、工兵中隊の本隊は、我々がいる洞窟からは約2キロ離れたマンドンに近い洞窟を拠点としていた。このボスネックの洞窟には、工兵隊の兵士は15名が入っていた。
記憶のある名は、
鎌田 分隊長
米谷仁吉 上等兵(秋田県出身)
晴山 兵長
熊谷正蔵 上等兵(岩手県花巻出身)
鎌田 伍長(岩手県出身)
渋谷惣作 兵長(山形県遊佐町出身)
藤巻二郎 一等兵、
瀬戸山晴治 一等兵(岩手県出身)
門山政明 上等兵(山形県松山町出身)
他の6名は思い出せない。
我々は長期戦を考慮し、木の枝や草等を洞窟に持ち込み思い思いの場所に寝床を造っていた。下は凸凹し、けっして寝やすい場所ではなかったが、草木でベットを造り工夫していた。
工兵隊にとって、こんなことはお手の物だった。この洞窟に入り三日たっても敵は現れず、「米軍は我々を怖れて、ビアク島には来ないよ」「戦艦大和も応援に来るらしいぞ」等と、未確認の饒舌を言う者もおり、一時的にも安堵した空気が流れ、酒を酌み交わす者もいた。
しかし、運命の日は確実にやってきた。
昭和19年5月27日の朝、米山仁吉上等兵が「顔を洗いに行こう」と私を誘ってきた。
洞窟を出ると、雲一つない澄み切った青空が広がり、南洋の朝日は眩しく美しかった。二人は椰子の木立の浜辺を歩きながら、引き潮の岩間から湧き出る真水を探していた。すると、遥か沖合に数10隻の船を発見した米谷が、「渋谷、我が軍も海軍記念日を期して攻戦に入るのかなー」と話しかける。
「海軍記念日」が制定されたのは、明治38年(1905年)5月27日、日露戦争の戦局の打開を目指し旅順港を封鎖されて身動きのとれないロシア大平洋艦隊を救出するために派遣された、当時最強と言われたロジェストウェンスキ−提督率いる、ロシアバルチック艦隊と日本海軍が対馬沖の日本海で遭遇。
2日間に亘る壮絶な砲雷撃戦の末、旗艦「三笠」に座乗する東郷平八郎元帥率いる帝国海軍連合艦隊が3隻を残しすべて撃沈。残る3隻もすべて捕獲するという大戦果を挙げた。この結果、ロシア海軍は事実上崩壊し日露戦争は一気に終結に向かったものであり、この大勝利を記念して5月27日を「海軍記念日」と制定されたのである。
 |
|
 |
| 洞窟入り口 |
|
洞窟内部 |
私も今日は「海軍記念日」だったことを思い出し、沖合に視線を移せば、アオキ島の手前に黒々と船が見える。
「どれが大和かな」と私も思いつつ、まだ歩き続ける二人を驚かせたのは、「ドドーン」という一発の砲音であった。それでもまだ、味方の演習かなと思いながら、立ち止まり見ていると、戦艦上から「パパッ」と赤い火花がはじけたと思うや、「ドドーン」と響き、空気を引き裂くような唸りを上げ、大きな砲弾が島に飛んできて大地を揺るがした。
二人は「敵襲」と叫びながら全力で洞窟に向かった。
昭和19年5月27日、午前4時30分頃のことであった。
その後は数秒たりとも絶え間ない艦砲射撃が、正午頃まで続いた。我々のいる洞窟は上陸目標地点の正面に位置しており、近くには何発となく砲弾が落ち、その度に洞窟が崩れ落ちる恐怖感が我々を襲った。
米軍は上陸に備え、徹底した艦砲射撃を行い日本軍の動きを制すると共に、戦意を奪う作戦をとったものと思う。
事実、米軍は各地の上陸作戦でも、「空襲」、「艦砲射撃」、そして「上陸」というパターンを踏み、自軍の犠牲者を最小限にする作戦を展開していた。
|
| |
|