敵は樹木の上にやぐらを組み、機関銃を据えて雨嵐のように撃って来る。
二日間の攻防も空しく、荒井平八郎小隊長は「中隊長殿、荒井小隊前進不可能」と叫んだ。
その声に中隊長は「馬鹿者、突撃・突撃」と軍刀を振り上げ、怒鳴った。仕方なく前進する工兵隊は、機関銃の格好の餌食となり、バタバタと倒れ全滅した。しかし、その後方にいた中隊長は死を免れたという。何とも割り切れないことである。この激戦の中には、私と同期生の酒田市飛島勝浦「なごし旅館」の分家にあたる、小隊長当番兵、鈴木芳郎上等兵がいたが、頭部貫通で即死した。
この戦いから数日後の、昭和19年7月2日、葛目部隊長(当時・大佐53歳)は自決し、その後は本国との通信は途絶し、我々は死を待つだけの部隊となった。岩手県一の関出身の、当時当番兵だった上関義一軍曹は、自決当時を述懐し、葛目部隊長は、副官と旗手の久村少尉と支隊本部付きの崩市太郎曹長を側に呼び、上関には「長い間お世話になった。君は必ず生きて帰り、四国高知(長岡郡)の実家にこの事を伝えてくれ」と話し、副官には「部隊長自決のことは誰にも知らせるな、以後の戦闘はゲリラ戦に転換するように」と指示、旗手の久村少尉には、「軍旗を焼いて敵には渡すな」等と言い残したという。
軍旗は、天皇陛下から各連隊ごとに直接手渡されたものであり、それを敵に渡すことは、どんなことがあろうとも許されることは無かったのだ。また、部隊に万が一の場合は焼却する建前であり、これを奉焼(ほうしょう)と言い、奉焼した部隊長は責任をとって自決することが不文律であった。
葛目部隊長自決の日を境に、連隊本部からの命令は全く無かった。それからは生きている者同士、ジャングルの中を彷徨い歩くだけだった。敵に出会えば交戦し、その度に仲間は減っていく。
今度こそ自分の番と幾度も死を覚悟したが、幸か不幸か生き続けた。
昭和19年7月中旬頃、生き残っていた工兵中隊は26名、無傷の者はたった8名であった。
我々、工兵中隊最後の戦闘は、昭和19年7月中旬頃と記憶している。米軍が、爆弾で壊れた飛行場整備に、戦車を先頭にトラックが骨材を満載して来るところに、生存者26名で肉弾攻撃を仕掛けたのである。我々は、攻撃直前に一升瓶に半分ほど残った酒を全員で飲み交わし、敵の戦車やトラックに蹄型式地雷を踏ませて爆破攻撃するために、飛行場に通じる道路脇のジュングル両側に潜んだ。しかし、一斉の攻撃もたいした戦果を上げることはできず、戦車やトラックの上から機銃掃射を受け、戦友はバタバタ倒れた。
我々は死に場所を求めていた。(●はここで戦死)
ここで当時の生存者と、肉弾戦参加者を記憶の限り記述する。
○ 佐藤長平中尉(士官候補生、大正10年生まれ、福島県国見町出身)
● 近藤 軍曹(青森県出身)
● 米谷仁吉兵長(秋田県出身)
○ 加藤友治兵長(秋田県出身)
○ 渋谷惣作兵長(山形県出身)・・生還
● 小原俊郎上等兵
● 滝島 上等兵
○ 阿部文治上等兵
● 大平盛雄上等兵(岩手県出身)
○ 千葉幸一一等兵(岩手県一関出身)
○ 粕谷(生還後三浦姓)辰治一等兵(山形県温海町出身)・・生還
○ 粕谷 博一等兵(山形県遊佐町藤崎出身)
● 安藤嘉吉一等兵
● 下坪清太郎一等兵(岩手県出身)
● 水平正治一等兵
○ 熊谷正蔵上等兵(岩手県花巻出身)
あと10名の氏名は分からない。
このとき、安藤嘉吉一等兵は、私の直近に居たが戦車砲を直撃され、一瞬にして消えるように吹っ飛び戦死した。
私も敵に約20メートル先から機銃掃射され、咄嗟に倒木の陰に身を潜めたが、その倒木は木片が砕け散るように粉々になりながらも我が身を守ってくれた。敵が通り過ぎてから弾痕を確認すると、倒木が無ければ間違いなく5〜6発は私に命中していた。
結局、この肉弾線で18人が戦死し、生存(○印)は中隊長以下8名だけであった。
ビアク島上陸当時、工兵中隊は約230名余いたのである。 |
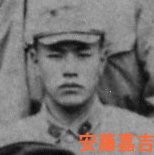 |
安藤嘉吉一等兵は、私の直ぐ
近くで戦死した |
|
私は、またも、幸か不幸か生き続けた。
この頃、阿部春治兵長は捜してもいなかったが、既に捕虜になっていたことは後に分かった。
なお、米軍はほぼビアク島を占領すると、直ちに飛行場の整備に着手していた。
我々が上陸以来3ヶ月以上かかって、人馬を使って造った約1キロの滑走路であったが、米軍はたったの数週間でブルドーザーを何台も使い、更に鉄板等を効率よく使い、短期間で3倍以上の長さに整備したのである。
この辺りにも、彼我の戦力差の大きさを、思い知らされたものだった。 |
|