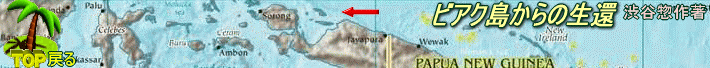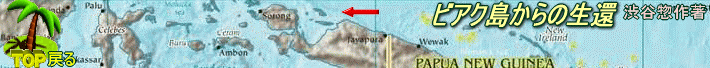|
| 著者 渋谷惣作 |
|
大正11年7月23日生
昭和17年12月1日初年兵として
盛岡工兵隊入隊
36師団「雪部隊」第222連隊所属
入隊と同時に北支に派遣され、更に昭和18年12月25日ビアク島上陸
陸軍・兵長「工兵中隊兼衛生兵」
昭和21年3月4日帰還
平成17年(2005年)8月18日没 |
|
明23・10・23〜昭19・7・2
高知県出身、陸士25期
大正2年12月
任歩兵少尉・近衛歩兵第4聯隊附
大正6年8月 任歩兵中尉
昭和14年8月 丸亀連隊区司令官
昭和16年4月高松連隊区司令官
昭和16年7月歩第222連隊長
昭和19年7月戦死(ビアク島にて)
中将「二階級特進」 |