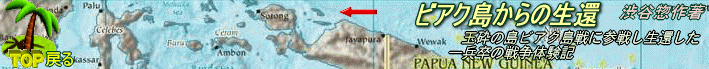 |
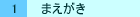 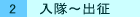  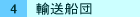 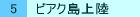 |
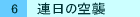 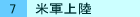 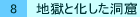 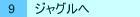 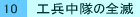 |
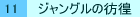 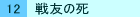 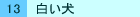 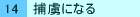 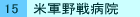 |
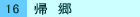 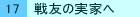 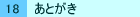 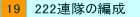 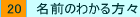 |
| 16 帰 郷(遊佐町〜野沢) |
昭和21年1月ころ、帰国の噂が流れた。
しかし、なかなか日程までは分からずに3月に入った。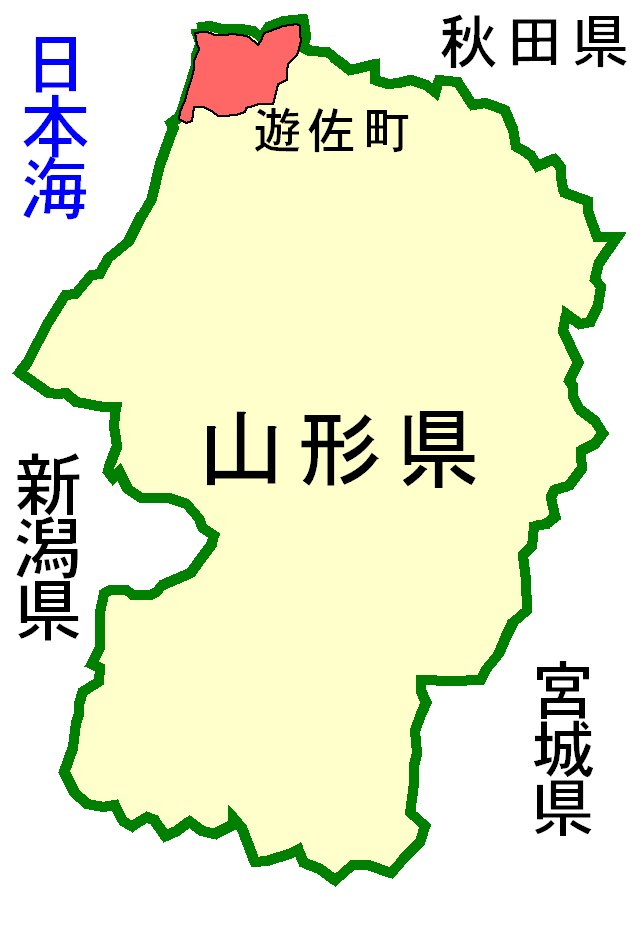
3月4日の点呼の時、「直ぐに帰国の準備をするように」との指示に、皆小躍りして喜んだ。
身の回りは、いつ帰国しても良いように整理しておいたが、いざ帰国となると、今までの苦しかったことが
走馬灯のように思い出し、この地も思い出深いものに思えた。
迎えに来た船は、「第一大海丸」であった。
この船は、まずオーストラリアのシドニー港で、アッツ島(昭和19年5月29日玉砕)の残留兵を乗せ、次に我々が居る、ポーランジァのフンボルト湾に立ち寄ったのであった。
昭和21年3月4日、第一大海丸は我々1千40名の日本兵を乗せ、祖国に向けて出航した。
ドラの音が高らかに鳴り響き、ニューギニア島を後にした。
戦友の顔が次々に浮かんでは消えた。
島影が見えなくっても、何時までもその方向を見ていた。
そして、出征からの4年半、余りにも失ったことが多かったことばかりを考えていた。
祖国に向かう航海は順風満帆であった。
南方に向かう時は、何時、魚雷攻撃や空襲があるかと、緊張の連続の船旅であったが、終戦から半年を経た今は、すっかり平和を取り戻した大海原であった。
それにしても、あの大兵団、大船団が1年程度で消えるように全滅してしまうとは?。ー
この戦争とはなんだったのだろう。
凄惨さと虚しさだけを残したこの「戦争」と言う二文字を、どう理解すれば良いのか、私のような一兵卒には整理も説明もつかなかった。 |
 |
| 故郷「山形県遊佐町」へ |
昭和21年4月3日、約1か月掛けて浦賀港に入港した。
入港してから半日もしてから上陸した。浦賀に上がった我々は、士官学校跡に2〜3泊してそれぞれの故郷に向かった。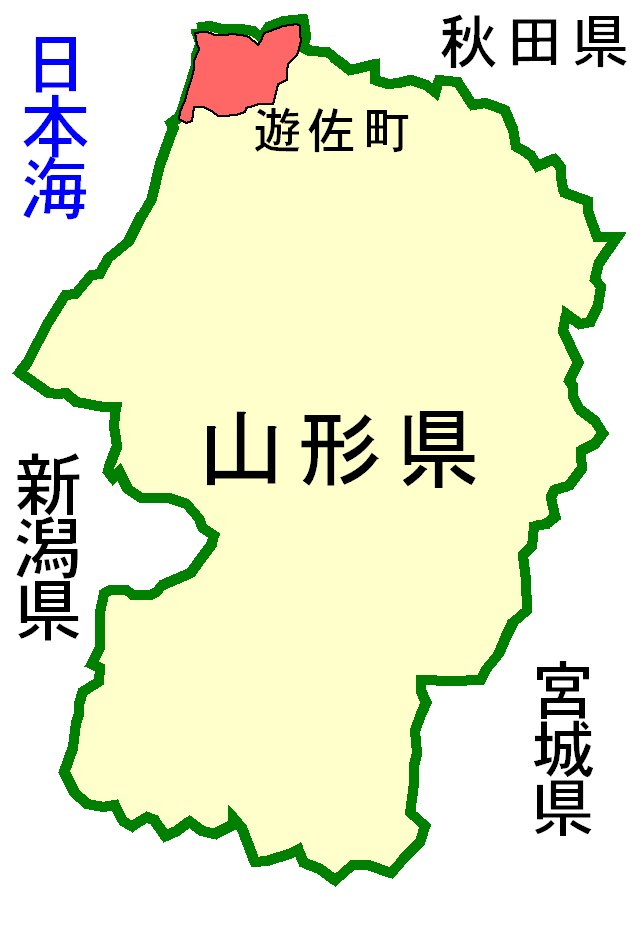
帰り際に支給された物は毛布を3分の1に切ったもの1枚、更に、我々東北出身者にはカンメンポウ(食パン)2袋、北海道出身者には白米3合とカンメンポウ3袋を支給された。その支給品を毛布に包み縄で縛り列車に乗った。列車の窓は破れて窓から乗り降りする人もいる。
列車内では朝鮮人の横暴な振る舞いが目に付いたが、戦地帰りの我々はじっと耐えるだけだった。
負けた国の悔しさが込上げてきた。
戦地に向かう前と比べ、人々の動きしぐさに明らかに変化を感じとれた。顔からは笑顔が消え、歩く姿からは活気を失っていた。
列車は、いよいよ羽越線に入り日本海沿岸を走り始め、見覚えのある景色が広がって来た。
私は海寄りの席に移り、一人で座りながら久しぶりに見る日本海の景色に見とれた。
祖父(丑太郎)の生家、府屋駅近くの海沿いの村、中浜も、以前と変わらぬ様子に安心した。
温海あたりまで来ると車内もユッタリしており、車内では母の歳に近い女性達が、懐かしい庄内なまり言葉で会話を始めた。
いっそう故郷が近いことが嬉しく思えた。
そのうち列車は庄内平野に入り、周りには田植え前の田園風景と、遠くには残雪を残した鳥海山がはっきりと見えてきた。
生家の野沢村は、鳥海山の麓である。
あの「ビアク島」でのことを思えば、二度とこの山を見れるとは思ってもいなかった。
鶴岡、酒田を過ぎ鳥海山はどんどん大きくなり、私は駅に着くのを待ちかねて立上がり出入口で山を見ていた。
列車はゆっくりと遊佐駅にすべり込んだ。 |
|
| 「遊佐町野沢へ」 |
昭和21年4月6日午後3時丁度、郷里の遊佐駅ホームに降り立った。
昭和17年11月30日この駅を一人出発し、4年半ぶりにひっそりと一人帰って来た。
まるで浦島太郎の心境であった。
まず、駅員が女性二人であったことに驚き尋ねてみると、戦争で男手が不足し女性駅員を採用するようになったと教えてくれた。
しかし、駅も町並みも鳥海山も、どこもかしこも変っていない。
本土空襲のことで心配していたが、まずは安心した。
ゆっくりと駅前広場に出ると人の目が気になり、店先の窓ガラスに姿を写して自分の服装などを見回して見た。
小豆色のシャツに赤色の捕虜ズボン、荒縄で縛った小荷物、髭は伸び放題、髪は肩まで伸びている。このままでは家に帰る気になれず、遊佐駅前の「石川床屋」に入った。
すると、客の爺さんが話し掛けて来た。
「どっちから来たでー」と言う。一目で帰還兵と分かったのであろう。
私は「南方のニューギニアから、今帰って来た。」と答えた。
爺さんは「ホホー良く帰って来れたのー」と感心してくれた。
遊佐町袋地の、佐々木久三郎のお爺さんだった。
「石川床屋」さんに、「どうぞ」と言われ、椅子に座り頭にバリカンを入れられたが、金は全く持っていないのに気付いた。どうするかと考えてたが、正直に「今、戦地から帰ったばかりで金を持っていない、明日持って来るから」とお願いした。
石川さんは、「いいよ、いいよ、今日はサービスだ。長い間ご苦労さん」と言ってくれた。
思うと「面付けない」ことであったが、以来、私はこの石川床屋は行きつけの床屋さんになった。
頭もきれいになり、母の従兄(野沢生まれ)が居る駅前の「大和屋」に顔を出した。
「いま帰った」と玄関で挨拶すれば、「ホッホー」と驚いているばかりであった。
丁度、野沢本家「松の助(訛って「マジスケ」)」の母さんも来ており、野沢まで一緒に帰ることにした。
野沢の家までの3〜4キロ位の道のりを、二度三度と座り込み休み休み歩いた。
女の足にもついて歩けない、自分の体力が情けなかった。
「やっばり弱ってるんだのー」と言われた。4月6日午後5時すぎ、4年半ぶりに我が家に着いた。
屋敷の入り口に立つと、母「鉄江」がサツマ芋の苗床を作っているのが見えた。
「今帰った」と声を掛けると、「惣作か、ホーお前、良く生きて帰って来れたのー」ただ驚くばかり、
足元を何度も見ては、足が付いていることを確かめていた。
この時のことは、後々まで笑い話になったが、私が生還することはすっかり諦めていた様子だった。
母は手荷物を私から取って家に入った。
祖父母も家にいた。
タ食時には家族全員が集まり、ささやかな歓迎を催してくれた。
周囲に身の危険を感ぜず、気を遣わずにする食事は久し振りだった。
帰ったら、あれも話そう、これも話そうと思っていたが、何から話せばいいか分からなかった。
弟や妹の成長ぶりには驚いた。
逆に家族から私を見れば、その変化にも驚いたことであろう。
私も20歳で出征し、幾度も死線を乗り越え生還した時は25歳近くになっていた。
更に、容貌を変化させていたのは、栄養失調で60数キロあった体重は半減し30数キロ、
まるで骨と皮の状態であった。 |
| 15 米軍野戦病院 |
 |
 |
17 戦友の実家 |
|
| TOPへ |
