この年表は、「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)の先代の佐藤俊明氏の記録によるものが殆どです。 野沢のタヨサマは「龍沢館」藤名五郎左右衛門の末裔で、1567年の戦で仁賀保の加茂氏に攻められ敗北後、藤名の姓を「佐藤兵部」と改め、以後、「御嶽神社」の社家として今日に至っています。野沢の歴史は古く、ここに載せた以外にも、古文書や昔からの言い伝え等の手がかりがあるはずです。なお、俊明氏は、2018年7月5日死去、享年78歳でした。 野沢のタヨサマは「龍沢館」藤名五郎左右衛門の末裔で、1567年の戦で仁賀保の加茂氏に攻められ敗北後、藤名の姓を「佐藤兵部」と改め、以後、「御嶽神社」の社家として今日に至っています。野沢の歴史は古く、ここに載せた以外にも、古文書や昔からの言い伝え等の手がかりがあるはずです。なお、俊明氏は、2018年7月5日死去、享年78歳でした。
右の写真は俊明氏(タヨサマ)と惣作がじゃれ合っている場面です。
なお、1817年の項や、ウメズサマなどの箇所を若干加筆しております。
|
|
 |
 |
 |
 |
| 御嶽神社鳥居 |
御嶽神社鳥居 |
御嶽神社 |
曹洞宗・安養寺 |
| ※ 原文の記録を重視した記載をしています。 |
1046年(永承2年)
現「御嶽神社」から南方約500メートルの地に、黒沢五郎正任が築いた「龍沢館」の広大な土塁跡が見られる。館の内に湧き水少なく、平時は井戸水の使用を禁じ、ここ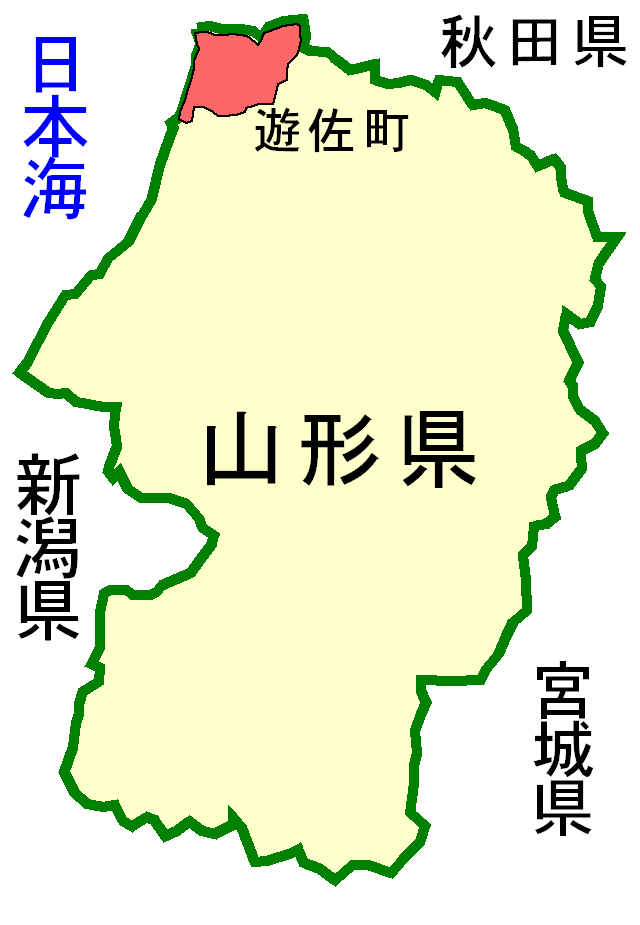 に雨池を造築、館の北門まで忍路(水路)を通じ水源を確保した。天池の東方僅かに突き出ているところは水神を祀った跡で、この池が龍沢館の重要な基盤であった。水利の不便もあり黒沢正任は、龍沢館の整備未完のまま、松岳山(現上寺地区)に移り、家臣「葛西勘十郎」が館を守ったという。 に雨池を造築、館の北門まで忍路(水路)を通じ水源を確保した。天池の東方僅かに突き出ているところは水神を祀った跡で、この池が龍沢館の重要な基盤であった。水利の不便もあり黒沢正任は、龍沢館の整備未完のまま、松岳山(現上寺地区)に移り、家臣「葛西勘十郎」が館を守ったという。
1187年(文治三年)
虚空蔵堂の山寺号に文治三年(1187)の銘がある鉾、承久2年(1220)銘の古鉾共に御頭行事に使用せるものなりと伝ふ。
1220年(承久2年)
出羽国風土略記に「蔵王権現、上野沢村山中に在り又滝沢権現共云う、社領十三石一升地方同村出羽守判物なり。社家一人有り、古鉾あり、承久2年神主正宇代」とあり。
又、出羽国風土記に、御社御嶽神社、祭神は少彦名命大己貴命二柱なり。野沢村水上に鎮座す。当社は大和国吉野郡金峰社を勧請せり。其年代詳ならざれども末社由良姫神社は、五十六代清和天皇定観年中(860年代)椿原の峰に社地を定め、隠岐国知夫郡由良姫大明神を遷し、里見和泉守橘正氏之を祭ると縁起にあり。然れば、本社創建は其前に在る事明なり。
1345年貞和2年
貞和2年「龍沢館」に藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。
※1345年当時は「南北朝時代」であり、様々の戦いが繰り広げられていました。最後は室町幕府三代将軍・足利義満が南北朝の仲裁に入り和平を結ぶ。結果は北朝に南朝が合流して統一される。タヨサマのご先祖の藤名氏は藤原氏系の公家の末裔と推測されます。1356年には斯波(しば)兼頼が羽州管領として山形に派遣され、姓を最上に代わります。
1443年 嘉吉3年
嘉吉3年「龍沢館」館主「藤名広盛」宝林庵を菩提処と定め、龍沢山「玉積寺」と改号す。同寺に嘉吉3年の銘のある鉄製雲板がある。県の重要文化財である。又、金銅阿弥陀如来座像は鎌倉期の彫刻、水滴は釉を使った瀬戸物でこれ鎌倉期のものである。
1449年頃(宝徳年中)
「龍沢山玉積寺」広盛宝徳年中に死す。法名を瑞雲院殿広法盛大居士と号す。其後「玉椿寺」と改む。 出羽国風土記に、安養寺、本尊釈迦牟尼如来を安す。野沢村久弥添に在リ酒田町海晏寺(かいあんじ)末なり。当寺は天正中道照法師の開基創建する所にして、元は村の東北なる龍沢山宝林寺と号せり。其履歴を尋るに道照法師諸国を論参して飽海郡に至る。龍沢山に雲龍石あり。其形獅子の如し。常に此石より雲生ず。故に、人此山を龍ケ獄と称す。
1567年(永禄10年)
「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に御嶽神社の流鏑馬神事の日に仁賀保大将の加茂惣左門に攻められ落城した。520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。
1588年天正16年
「龍沢館」の家臣は、元々館の麓、野沢村で農を営なみながら武芸に励んで ものであろう。
郡誌に「其後度々夜盗あり。天正16年仁賀保仙北より夜盗共5〜60人余参り候て・・・・60人討止め申し候」等とあり。今も当時を語るゆかりの地がある。藤井新田の旗引沢、馬立森、下野沢の石塚をはじめ、安養寺の前は玉石を敷き詰めた馬場であり、拝殿前の土塚は戦死者のものであろうか、白旗屋敷は今の新十郎(しんじょろ)の処で、蔵人小路、観音小路などの地名が残っている。今の岡家は「岡九右工門」の跡であろう。
1612年(慶長17年)
慶長17年6月4日、最上義光(よしあき)ヨリ灯明供物料トシテ拾壱石一斗一升ヲ寄附セラル。
※最上義光は最上氏第11代当主、戦国時代から江戸時代前期にかけての出羽国の大名であり、出羽山形藩の初代藩主です。1622(元和8年)最上家のお家騒動で領地を没収され、酒井忠勝が信州松代から鶴岡に入部する。
1634年(寛永11年)
「上野沢新田」「下野沢新田」は欠落農民が帰還して開発・入植した。他にも同時期に、北目新田、大楯新田、天神新田、平津新田が同時期に欠落農民によって開発・入植した。欠落の理由は「寛永の飢饉」から年貢納入が出来ず、1622年から8年間で遊佐郷だけで数千人が身売りして村から消えた。
下野沢の「高橋太郎左衛門目安」から
1624年頃(寛永年中)
「滝沢山玉椿寺」寛永年中、本寺第八世祖天長老再興して、曹洞宗に転じ「安養寺」と更む。
※「安養寺」の建立は、江戸初期の1612年(慶長17年)に幕府はキリスト教禁止令を出し、以後、全ての庶民は何処かの寺に属して、いわゆる「檀家」となって、その「菩提寺」に葬儀や供養を依頼する制度が全国に広まった時期と重なります。
1659年(万治2年)
「御嶽神社」拝殿を修造。「吹浦御林ヨリ用材ヲ下シ置カル。」
1672年 江戸の商人河村瑞賢は江戸の急激な人口の増加に対処する為、内陸の幕府直轄地からの米を送る為の調査と実行を幕府に命ぜられて一行56人と共に加賀屋に泊まった。
1681年頃(天和年中)
曹洞宗「安養寺」天和年中、霊松長老、現地に移転す。
1689年 芭蕉が奥の細道の紀行中酒田の俳人伊藤不玉宅(鐙屋の裏に住む藩のおかかえ医師)に滞在する。
1739年(元文4年)
「御嶽神社」本社拝殿を造替、藩主米30俵寄進、日を経ずして拝殿焼失の厄に遇い、以後、末社を拝殿に使用してきた。
1804年 鳥海山噴火で、西の松島と云われた象潟(秋田県由利郡象潟町)が隆起する。飽海田川郡で被害死者があり、死者333名、倒壊家屋5500軒、酒田では津波で浸水家屋300軒。
1804年頃文化年中
文化年中、大庄屋斎藤隼之助は自宅で読み書きを教え、その門人梅津久米治その後を承りて30人ばかりの子弟に教えた。隼之助の子・太郎八その後をつぎ、更に久米治の弟梅津曾六郎は兄の志をつぎ教師の役を引き継ぎ、明治の学制頒布を迎えた。「野沢学校」の前身である。
「梅津曾六郎」は善民ではなかろうか。
1813年文化9年
酒田の「白崎五右工門」瓦工場を野沢山にはじめる。
高岡善平は京都より白崎五右工門を頼り同家に奉公していたが、瓦工場を創める時、京都から来た瓦師白崎某と共同経営をした。窯は内川の北岸渋谷七太郎(シジダロ)の東後の畑の辺である。
やがて白崎家は袋地に移ったが、高岡(かわらえ)は村に土着した。
1817年(文化13年)
だんな様屋敷は石垣(長作)の処で、江地組大庄屋・斎藤隼之助、文化13年此処に住し、文政元年(1818)同七大夫横山組より来て相続した。次いで孫源右工門、朝道と子孫相承け維新後に至っている。その子孫は八日町に住んでいる。曹洞宗の安養寺門前には最後の大庄屋の碑がある。
1840年(天保11年)
酒井侯、長岡藩転封事件(天保一揆または天保の義民と呼ばれる。詳細は「義民が駆ける」)の時、同12年3月21日若年寄増山弾正少弼に善作(家号ゼンサク)、同6月25日佐竹侯に善九郎(家号ゼンクロ)が陳情に参加している。(鶴岡出身の作家・藤沢周平は、小説「義民が駆ける」の「領内騒然」項で「天保の義民」として紹介している。陳情の目的は、万が一、幕府が近隣の藩に庄内藩取り鎮めを命じた場合、その藩主に庄内藩の百姓の気持ちを分かってもらうことであったと分析している)

1857年(安政5年)
コレラが流行し、野沢村でも多くの死者を出す。普通の墓地に埋葬出来ないので、村の北東広野に近い所に埋葬する。経塚森付近にコレラ墓が散在する。
※12〜3歳頃一度だけ、この石碑を見ています。それを祖母に話すと、失礼ながら「あそこは近寄らねもんだ」と注意されたものです。石碑は放置された印象でしたが、感染症やコロナ禍のおり、村人は警鐘を鳴らす意味でも、あらためて祀ってあげることも大切と思っています。(正確な場所は不明です)
1874年(明治7年)
明治7年12月、「石垣善九郎(ゼンクロ)」は郵便取り扱いを開始した。
野沢簡易郵便局は、昭和41年5月16日開局で菅原三治郎が初代である。
1876年(明治9年)
「御嶽神社」は明治9年より郷社に列す。祭日は3月13日、9月13日の両度なり。椿原の峰は本殿のある処である。
※ 同年に、「上野沢村」「下野沢村」「下野沢新田村」が合併して野沢村が誕生。野沢は今も、上・中・下に分かれていますが、根拠があることです。その後も、憲法発布の明治22年に、遊佐町村・白井新田村・野沢村・吉出村・小原田村が合併して「遊佐村」が誕生し、昭和29年に遊佐町と他5村が合併し遊佐町が発足しています。
1893年(明治26年)
御嶽神社鳥居前に「梅津善民碑」がある。明治26年3月、裁縫門人の建てたものである。
※1804年頃文化年中
文化年中、大庄屋斎藤隼之助は自宅で読み書きを教え、その門人梅津久米治その後を承りて30人ばかりの子弟に教えた。隼之助の子・太郎八その後をつぎ、更に久米治の弟曾六郎は兄の志をつぎ教師の役を引き継ぎ、明治の学制頒布を迎えた。「野沢学校」の全身である。野沢学校は今の「シンジョロエモジ」のところ。
1902年(明治35年)
内川は屈折甚だしく、大雨の度に洪水になった。明治35年に改修に着工し同37年4月に竣工した。古川跡は暫く沼地として残り、魚釣りをしたという。
※内川は古川とも呼び、シンジョロエモジ、トダエモジ、ウシエの南側を流れていた。長く水溜まりが残っていた。
1907年(明治40年)
高瀬川の鮭の孵化事業は明治40年より始められた。
組合員は上野沢、下野沢、富岡、北目、京田、丸子の人達で、二組に分かれ孵化場も柳本と下の二カ所であった。やがて組合員も少なくなり組合も一緒になり、孵化場も一カ所になる。八幡様の清水を使っていた。
1914年(大正3年)
茶山又宗興、本名「渋谷小太郎」、東田川郡長沼生まれ、石垣熊太の知遇を得て、大正3年野沢村に移住、南宗派の絵を描き書もよくし、又障子張りをして生活した。
遊佐小学校の「遊佐の四季」は逸品である。(合併後の存在は把握していません)
1954年(昭和29年)
野沢下久ネ添44「伊藤源八(ゲンパチ)」で井戸掘り中、古銭のびっちり入った木箱が出土した。百貫文はあったという。今も一部は中央公民館に保存されている。
最古のものは紀元前175年から1310年までの古銭で46種に及んだという。
1954年(昭和29年8月1日)
遊佐町・稲川村・西遊佐村・蕨岡村・高瀬村・吹浦村の、一町五ヵ村合併で「遊佐町」が誕生する。
1956年(昭和31年)
1739年(元文4年)に消失していた「御嶽神社」拝殿を再建し、現在に至る。
1959年(昭和29年9月から昭和33年8月までの4年間)
遊佐町初代町長に、野沢村ハチジョロの「渋谷八三郎」が選出される。
※以後、村内からは町会議員も出ていません。立候補者も皆無だったそうです。
1966年(昭和41年)
野沢簡易郵便局は、昭和41年5月16日開局で菅原三治郎が初代である。
2018年(平成30年)
野沢のタヨサマ佐藤俊明氏は、2018年7月5日死去、享年78歳でした。
現在のタヨサマは長男が継いでいます。
2024年(令和6年)7月25日
線状降水帯発生による大雨で野沢川が氾濫。ヨハジロやハチジョロ辺りの堤防が損壊される。
改修工事に半年の期間を要した。
2025年(令和7年5月25日
野沢川、地抜川が二級河川に昇格した。
|
 |
|
| 〒999-8303 山形県飽海郡遊佐町野沢上ク子添 - Google マップ |
|
|
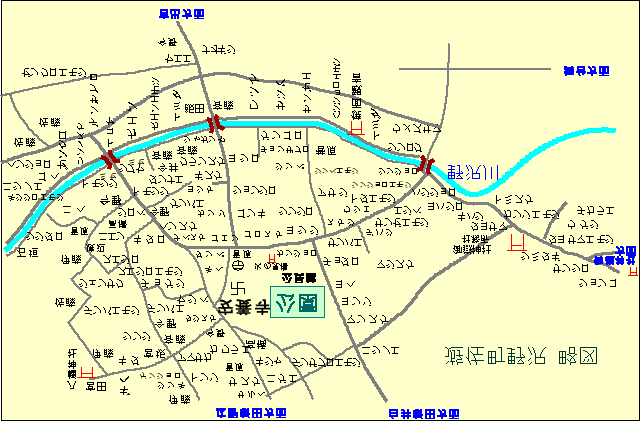 野沢の家号が分からないと、歴史の内容が良く理解出来ないと思います。しかし、野沢の皆さんなら、全ての家号をご存じのはずですから、必要ないと思われます。 野沢の家号が分からないと、歴史の内容が良く理解出来ないと思います。しかし、野沢の皆さんなら、全ての家号をご存じのはずですから、必要ないと思われます。
それでも、すでに「家号」入りの地図は作成してありますが、万が一、事件や電話による詐欺事件、セールスなどに利用されたら困りますので、右のようによく判別出来ない程度に縮小し、更に反転しておきます。もっとも、「ゼンリンの住宅地図」を見れば、個人宅は簡単に確認出来る時代ですから、皆さん気を付けて生活して下さい。 |
